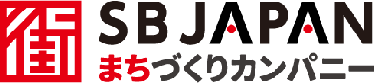インバウンド観光の現状と未来
近年、円安やビザ緩和の影響もあり、日本には多くの海外観光客が訪れています。インバウンド観光によって日本の企業は潤いを見せていますが、それと同時にさまざまな課題が生まれつつある点も事実です。
そこで今回は、インバウンド観光について、地域活性・グローカル事業、ならびに輸出・輸入支援事業や文化コンテンツ事業を手がける**「エスビージャパン株式会社」の中元社長にお話を伺いました。

ツバル高校にて教頭と意見交換
エスビージャパンの事業について
ーインバウンドに注力するようになった理由や背景を教えてください。
2007年に会社を立ち上げた当初は、国内の地域活性化や地方創生をメインに事業を行ってきました。
しかし、2020年にコロナが流行し始めた頃からコロナ終了後の観光の移り変わりを意識し始め、現在は海外観光客のインバウンドプロモーションや地方自治体・企業の海外進出支援、インバウンド観光客の地域整備、プロモーションに力を入れています。
コロナ禍が落ち着いたことで、日本には海外から観光だけでなく働きに来る人も増加しました。そのため、このタイミングで日本の良さが上手くグローバルに結びつけば、地方創生や地域活性化がより勢いづくと思っています。
ただし、ローカルの良さを再認識しなければ、ただ海外観光客や移住者に迎合するだけになってしまうので、グローバルな視点を持ちつつ、ローカルの良さを守っていくことが大切だと思っています。
ーインバウンド観光における「今ならでは」の変化はありますか?
インバウンド観光は、海外観光客を呼び込み、とにかく日本の経済を活性化させることが第1フェーズだったとすると、現在はゴミや交通ルールなどの社会問題、オーバーツーリズム、日本人と海外観光客のコミュニケーション不足など、さまざまな問題解決に動く第2フェーズにさしかかっていると考えています。
そのため、これからのインバウンド観光は、観光事業に携わっていない地域住民の方々と、海外観光客、両方の視点で問題をくみ取り、双方が快適に過ごしていくにはどうすれば良いかを考えていくことが大切だと思います。

昔ながらの原風景が残る街並みを大切にしたい
海外観光客が求める体験とは?
ー今、日本に来ているインバウンド観光客には、どのような体験や場所が人気だと感じますか?
日本では、一般的に相撲体験や刀造体験、忍者ショーなどの「コト体験」が海外観光客に人気と言われていますが、実際の声を聞いてみると、「高架下やガード下の居酒屋に行ってみたい」「空手道場の躾方法を見てみたい」など、ローカルな体験を好む方が多い印象を受けます。
そのため、海外観光客向けにつくられた「ザ・日本」といった特別なショーや食事ではなく、私たち日本人が普段から楽しんでいるローカルな場所や体験のほうが、実は需要が高いのではと考えています。
-日本人にはあまり想像がつかない意外な場所や体験が、注目されるということですね。
そうですね。日本人でも現地の人が楽しむところへ行きたいと思う人が多いように、海外観光客もそう思う人が多い印象です。
ただし、海外観光客は日本人とコミュニケーションを取りたいと思う人が多いなか、日本人は英語が苦手ということもあってか、コミュニケーションを取れない場面が多く見られます。そのため、日本人と海外観光客の方が気軽にコミュニケーションを取って行ける環境を整備できると、より良いなと思います。

ネオ居酒屋など昔ながらの商店街、繁華街にも注目しています
観光業界の課題と改善点について
ー日本の観光地や観光サービスにおいて、どのような点が強みだと思いますか?
物静かで謙虚なところや、治安が良く、道ばたにゴミがほとんど落ちていないところなどが、日本の強みだと思っています。
また、ご当地グルメや体験の細分化など、これだけ情報や観光事業が豊富にあるなか、細かくカテゴライズできている点も、日本の強みですね。
ー「もっと改善できる」と思うものがあれば、教えてください。
日本の観光地や観光サービスは、外国人の不便さを過度に改善しすぎだと感じます。
特に、駅の案内板や観光地の説明文などは、多言語化しており、かえって不便です。海外の人に話を聞いても、そこまでのサービスは必要としていない人が多いばかりか、逆にもっと日本語を見たいと言っている人が多かったので、この点は改善点だと思います。
-本当に必要なサービスを見極めることが大切ですね。
海外観光客は、自国とまったく違う文化を楽しむために日本へ来ているため、言葉の不便さを楽しむのも旅行の醍醐味だと思います。実際に、私が知る老舗のお好み焼き屋はメニューがすべ日本語表記ですが、来客の9割は海外観光客の方で、みなさんスマホの翻訳機能を使いながら日本語や日本の文化を楽しんでいらっしゃいました。
-世界各国で行われているインバウンド向けの事業で、「これは良い」と感じたものがあれば、教えてください。
ターミナルや空港は、案内板が設置されていても海外観光客にとって詰まりやすい場所なので、タイやフィリピンなどでよく見かけるツーリストポリス(ツアーの案内人)を日本も配置すると良いと思います。
また、主要な観光地にツーリストポリスを配置するのも良いですね。現在、観光地によっては海外観光客が周辺の商店へ英語でいろいろ尋ねに来て困っているといった話も聞くので、ツーリストポリスの配置は観光地で働く日本人の不満解消にも繋がるでしょう。
-ツーリストポリス以外にも「これは良い」と感じたものはありますか?
ソウルに設置されている外国語同時対話システムも便利だと思いました。
外国語同時対話システムは、ガラスにお互いの会話がリアルタイム翻訳を通じて文字表示されるので、違う言語を使う者同士もスピーディーに会話できます。表示される文法は正確でないかもしれませんが、インバウンド観光が盛んになっている今、路線バスや駅、空港にあると便利だと思います。

海外でもよく見かける多言語 どこまでを翻訳すればいいか
■今後の注目すべき観光ニーズについて
-インバウンド観光のなかで、今後特に注目されそうな体験や場所はどのようなものだと思いますか?
宿場巡りは、今後インバウンド観光で注目されそうだと思っています。
宿場は、日本の歴史や街を知ってもらうには打って付けの場所です。愛知県に残っている二川宿や、三重県にある関宿は奇跡的に現存している宿場であり、特に関宿は江戸の町並みがそのまま残っているような風情を楽しめます。
宿場町はゲストハウスがあるにも関わらず、現在は観光客が少ないので、日本の文化や日本語に触れたい海外観光客から人気が出ると考えています。

関宿、大内宿、二川宿など、宿場はこれから盛り上がると予測
-ほかに注目されそうな場所や体験はありますか?
ゲームの影響もあり、現在は海外にも織田信長や真田幸村などの武将ファンが多くいらっしゃるので、武将由来の土地を外国人向けに整備すると、地域起こしになると考えています。
武将の固有名詞を軸に、合戦地や生誕の街を巡ったり、昔ながらの食事を楽しめる体験を用意したりして、そのまま宿場巡りを楽しめるコースを組むのも良いのではないでしょうか。
また、巡礼旅も今後注目される体験だと考えています。
実際、私が四国88か所、西国33か所などを満願した際、欧米からの旅行者が長期間で歩き遍路をする姿を各地で見ました。そのため、フォトスポットとしての神社仏閣巡りだけでなく、文化をしっかり理解してもらう巡礼旅も人気が出る可能性があると思います。

四国遍路などの巡礼旅は欧米豪からの旅行者に注目を集めている
-インバウンド観光をビジネスとするうえで、今後どのような可能性があると考えていますか?
今後は主要観光地だけでなく、日本の「カテゴライズ」の深さを、インバウンド向けにどうやってプロモーションしていくかが大切だと考えています。
具体的には、宿場巡りやお遍路巡礼など日本の風景を楽しむ体験、ガード下のように昭和の雰囲気を楽しめる居酒屋巡りなどに勝機があるでしょう。
地域活性化の未来に向けて
ーエスビージャパンが今後注力していく地域活性化の事業について教えてください。
私たちは今後、観光業だけでなく、地域づくりに関するプロジェクトにも力を入れていきます。
地方の伝統や文化を守りつつ、未来志向で新しい観光体験を創造することが重要です。また、地域の観光資源だけでなく、地方で働く人々や企業を巻き込んだエコシステムの構築にも注力していきたいと思っています。
ー日本の観光業や地域活性化が抱える最大の課題は何ですか?
最大の課題は、持続可能な観光と地域活性化のバランスだと感じています。
観光業は確かに経済を支える重要な柱ですが、観光地が過度に観光客に依存してしまうと、地域住民の生活や環境が脅かされる可能性があります。そのため、地域に密着し、観光と住民の生活が共生できる仕組みづくりが不可欠だと考えています。

世界中からの旅行者から集うタイムズスクエアを視察
■最後に、これからインバウンドを対象としたビジネスに取り組もうとする人たちに向けて、メッセージをお願いします。
ビジネスを始めると、つい事業者目線になりがちですが、常に意識をアップデートしながら旅行者の目線に立ち「自分だったらどう思うか」といった気持ちを忘れないことが大切です。
私も観光情報やトラベル系のニュース、海外の方のSNSは毎日リサーチし、気になる情報があれば自分の足で体験して消化するようにしています。実際に行くとわかる部分もあるので、気になる情報があれば、まず自分で経験してみてください。
今後も自分の経験や体験を軸に各自治体と連携し、ご要望があれば講演会にも挑戦していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

ツバルの小学校の授業を視察

東京ゲームショウにて さまざまなイベントにも積極参加

Route66 3か月をかけて全米全州を走破